
株式会社はりゅうウッドスタジオ
株式会社はりゅうウッドスタジオは、福島県南会津町に位置するアトリエ設計事務所だ。標高約700メートルの中山間地に拠点を構え、この地で2006年より地域に根差した建築を手掛けてきた。東日本大震災では木造仮設住宅の設計・建築に尽力。その経験をきっかけに、地域と社会に寄り添う公共建築への参画も広がっている。今回は、BIMソフト「Archicad」の導入により、ローカル拠点のハンデを武器に変えていく取り組みについて、代表取締役であり一級建築士の滑田 崇志氏と、一級建築士の斉藤 光氏に詳しく伺った。
所在地:福島県南会津郡
代表者:滑田 崇志
創業:2006年
業務内容:
建築に関する設計監理業務、コンストラクション・マネジメントに関する業務、建築に関する企画、出版物の企画ほか

代表取締役
一級建築士
滑田 崇志 氏

一級建築士
斉藤 光 氏
標高700m からの挑戦。
ローカル設計事務所を武器に
「東京の設計事務所と比べたとき、私たちのような地方の事務所は“選ばれにくい”という現実があった」と語るのは、代表取締役の滑田 崇志氏(以下、滑田氏)だ。はりゅうウッドスタジオの会津本社は、標高700mにある。毎年冬になると一晩で1m以上も雪が積もることも珍しくなく、町の面積の9割以上が森林という自然豊かなエリアに位置する。古くから南会津町は林業が盛んで、会津本社の近くには製材所もある。「この地に事務所があることで、木のことは都会の設計事務所よりも深く理解できる。地域の森林資源と加工技術を活用することを会社のブランドとして設計活動をしています」と滑田氏。
このように、あえて“標高700メートルの設計事務所”という個性を前面に打ち出し、中山間地からBIMというテクノロジーを活用することで、場所を選ばない設計手法へと舵を切った。

会津本社は1916年(大正5年)建築の「阿久津家住宅店蔵」を事務所に改装。国指定の登録有形文化財でもある。
合理性と将来性を直感し導入を決断
Archicadを本格的に導入したのは、2016年頃。きっかけは、「ちょっと面白いソフトがある」と共同経営者であった芳賀沼整さん(2019年に逝去)に強く薦められたことだった。当時使っていた2D CADでも満足に設計業務は行えていたが、営業担当者から話を聞くと「BIMを導入することが、設計事務所の将来に生きてくる」というイメージがすぐに持てたという。「営業担当者から海外の事例を聞きました。私たちと同じ、山間地にある小規模設計事務所が、Archicadを使って大規模設計をしているとのこと。当時、リモートでの設計のやり取りにも課題があった私たちは、BIMを使うことで解決策が見いだせると期待しました」と滑田氏は語る。
また、BIMに興味を持ったのはそれだけではない。当時使っていた2D CADでは、図面の整合チェックに膨大な時間がかかっていた。「二次元で設計すると、必ず間違いが起きる。私は、そのチェックに時間をとられることが非合理だと感じていました。確認作業に時間が割かれるのなら、もっと創造的な時間に使いたい」。同社では、BIMに合理性と将来性を直感し、導入を決断した。

「営業担当者のプレゼンを聞いたときに、そのときすぐにBIMの可能性を感じました」(滑田氏)
設計と施工の橋渡しとしてBIMは確かな効果を発揮
Archicadの本格運用は、三重県内のある医療施設でのプロジェクトから始まった。設計担当者は、当時産後休暇から戻ってきたばかりの斉藤 光氏だ。それ以前は、若手スタッフを中心にBIM習得を進めていたが、基本設計はできても実施設計に至らず、現場での運用には課題が残っていた。「トレーニングを受ければすぐに実務で使える」と考えていたが、実際には現場に即した理解と、実務を通じた試行錯誤が不可欠だったという。
そのようななか、医療施設プロジェクトをBIM設計の初案件として取り組むことに。プロジェクトは複雑な外観形状と施工上の課題が重なる難易度の高い内容だったが、設計と施工の橋渡しとしてBIMは確かな効果を発揮した。「このプロジェクトは、基本設計を別会社が行い、私たちは、縦ログ構法による実施設計を担当しました。BIMを使うことで複雑な曲線が連続するディテールの設計も正確に設計ができました。
実務の中で使い倒したからこそ、『2D CADではなくすべてBIMでやっていける。やっていこう!』と確信につながりました」と、斉藤氏は振り返って話す。

「初めてのBIM案件でも複雑な曲線が連続するディテールの設計ができました」(斉藤氏)

外部のBIMマネージャーと協業した、須賀川市の中心部の丘陵地に立つ「認定こども園らみどり」のプロジェクト。
情報共有と検証のための「設計の共通言語」
またプレゼンテーションツールとしてもBIMは強力だ。これまで建築プロジェクトでは模型をつくることが「よい建築をつくるために必要不可欠な過程」とされていたが、BIM導入後はその役割の多くをBIMの3Dモデルが担っている。BIM上で、建物形状、空間性、使い勝手、採光や通風、温熱環境や照明計画など、さまざまな環境シミュレーションをもとに設計を検討できるためだ。「現在進行中のプロジェクトでは、BIMから構築したVRを使って、設計中の建物内部を体験できるようにしています。設計段階から建物の中に入り込み、『ユーザーはどのように感じるか?』を、私たちも、クライアントもリアルに把握できるようになりました」と斉藤氏。
モデルを共有しながらリモートで設計業務を協業
また、宮城県の富谷市図書館等複合施設(ユートミヤ)プロジェクトでは、東京の有限会社ナスカ一級建築士事務所とJVを組み、共同で設計に取り組んでいる。ここでは設計を役割分担で業務を行うのではなく、ひとつのモデルを共有し、Zoom上でリアルタイムに意見を交わしながら同時に設計を進めるスタイルをとった。
福島と東京の遠く離れた設計事務所同士であっても、チームワーク機能を活用することで、常に最新情報を共有しながら設計業務が可能になる。「東京と福島の遠隔地であってもチームワークを活用することで最近の検討案を共有でき、総合的な検討がしやすい。さらにデータ管理・ファイル管理がとてもスムーズになりました」と斉藤氏。
また、別のプロジェクトでは、外部のBIMマネージャーに参加してもらうことで、情報の出し入れや作図方法に標準ルールを作ることができた。「それまでは我流でやっていました。BIMマネージャーに入ってもらうことで、我流では見えなかった部分に気づける貴重な機会になりました」。
基本設計から実施設計に至るまで、都心と山間のアトリエが同じプラットフォームで議論を重ねる。遠く離れた二つの事務所でもBIMだからこそ可能になった、新しい建築設計のかたちである。


有限会社ナスカ一級建築士事務所(東京)とJVで実施している富谷市複合図書館(ユートミヤ)プロジェクト。VRを活用した空間検討も行われている。
第23回緑化技術コンクール環境大臣賞を受賞した、日大ロハス工学センター棟ロハスの森「ホール」
小規模設計事務所のためにBIM連携を推進
同社は、福島県建築設計協同組合の「DX委員長」としてもBIM普及に尽力している。福島県内では現在、組合加盟会社44社のうち約24社がArchicadを導入しており、その輪は着実に広がっている。「小さな設計事務所同士が協力し合い、実施設計まで対応できるBIM活用力を育てたい。BIMは私たちが一社だけで使えても意味がありませんから」と滑田氏。
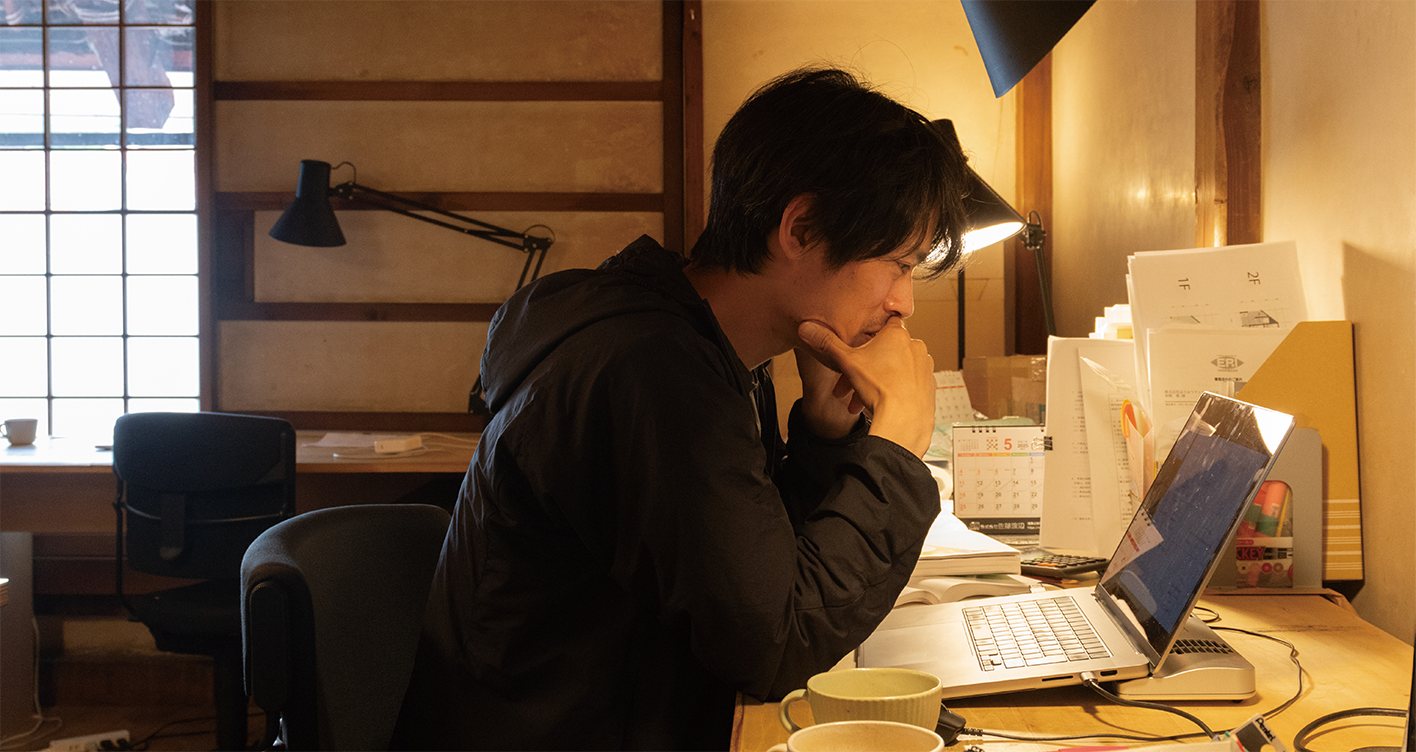
はりゅうウッドスタジオには若手設計者が集い、それぞれBIMに触れる機会を得ている。「ここでの経験が、どこの事務所に行っても通用するBIM人材につながるはず」と滑田氏は若い設計者たちへの期待を込める
県内でのBIM普及のために、同組合のDX委員会では「BIM設計実務研修会」を企画・開催した。講師には、熊本を拠点に活動するグラフィソフト認定コンサルタント・道脇 力氏を招き、13回にわたるオンライン講座を実施。対面式でも行い、より実践的な学びを提供した。「大手設計事務所と肩を並べるには、小さな設計事務所同士が連携することが大切。BIMを活用することで、どんな規模の設計事務所でも大きな公共建築に関われる時代を作りたい」との想いも熱く語る。
少子高齢化にともなう人手不足が深刻化する中で、設計事務所の少人数化は今後さらに進むと見られている。そうした状況においても、BIMを活用することで、少人数でも高精度な設計を実現できる体制づくりが可能になる。BIMは、地方の設計事務所にとっても、業務の質と効率を高めるために欠かせないツールとなりつつある。

2024年に開催された「BIM設計実務研修会」。組合員32社69名と福島県技術職員が5名オブザーバーとして参加。興味関心の高さが見てとれた
BIMは手段。
目指すは”思考をジャンプさせる建築”
「BIMはあくまで道具。でも、それがあることでより、一分の一の立ち方に対して確信を得ながら設計ができる」。そう語る斉藤氏は、設計業務の効率化により、模型づくりなどの物理的負担が軽減され、「その分、より良い提案に頭を使えるようになった」と実感を込める。
はりゅうウッドスタジオの設計思想の一つには「一つひとつの建築で人々の暮らしや思考をジャンプさせること」と掲げる。そのためには、共有し、理解し、納得してもらえる設計が不可欠であり、BIMはその大きな助け舟となっている。「例えば模型づくりは、これまで学生に頼っていた部分も、地方ではマンパワーは少なく簡単ではない。でもBIMがあれば、少人数でも模型と同様の価値あるツールが作れます。そのように効率的で高精度な設計ができることで、小規模設計事務所の可能性が広がっていくはずです」と滑田氏。
さらに「人口が減少していく時代だからこそ、小さな設計事務所や地域の組織がつながり協力し合うことが、地方の未来や社会のあり方を前向きに変える力になると信じています。私たちは、そんなネットワークを広げていきたいと考えています」と締めくくった。

整然と木の柱が連なる模型内観

はりゅうウッドスタジオで設計を行った
「みなみあいづ森と木の情報・活動ステーション きとね」の模型と一緒に
「きとね」は、豊富な森林資源と加工技術を最大限に活用し、オール南会津で作り上げられた施設
Archicadの詳細情報はカタログをご覧ください
ー カタログと一緒にBIMユーザーの成功事例もダウンロードできます ー
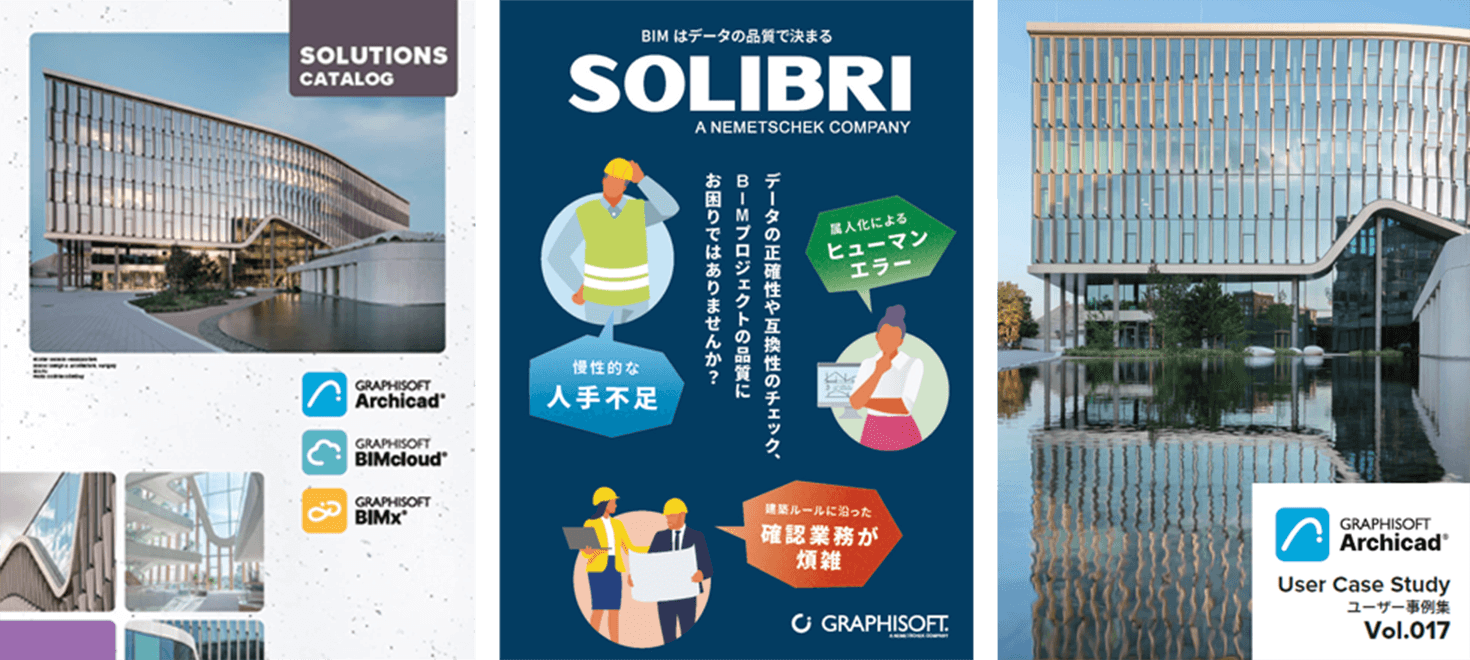
- Archicad ユーザーの設計事例を紹介
- 設計時の裏話や、BIMの活用方法など掲載
- その年ごとにまとめられた事例をひとまとめに
- BIM導入前から導入後の情報満載



